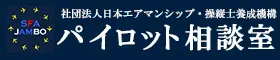ステイ先で学ぶ政歴シリーズ 海外編11〜インドネシア 「超」親日国インドネシア〜第3章
インドネシア独立戦争
1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、終戦を迎えました。
ボルネオ島を除くインドネシアの領域内では連合国軍の攻撃が殆ど行われなかったため、駐留日本兵もインドネシア人も日本が負けたことを実感できなかったと言います。
日本が降伏したことにより、独立の悲願が無に帰することを恐れたスカルノは日本降伏の2日後の8月17日、インドネシア独立を宣言しました。
しかし、旧宗主国のオランダはインドネシア独立を認めず、再び植民地化しようと軍隊を差し向け、スカルノ政権を鎮圧しようとしました。
そうしたオランダの動きに対して、日本が降伏後に解散となったPETA出身者らが立ち上がり、再集結してインドネシア国軍を組織しました。
この時、日本軍は降伏して武装解除したものの、武装を連合国軍に引き渡さず、「重火器はインドネシア人に奪われてしまった」とインドネシア国軍兵士が武器を取っていくのを眺めるだけという、事実上武器の横流しを行なって日本本土に帰国していきました。
また、約3000人の日本軍将兵が日本に帰国せず、インドネシア国軍に合流し、インドネシア人と共に独立を勝ち取るためにオランダ軍と戦いました。
残留日本兵は常に最前線で戦い、1000人以上が戦死したといいます。
日本軍の武装を手に入れ、多くの残留日本兵が合流したインドネシア国軍は非常に強力な軍事組織となり、本国が戦時中に荒廃したオランダ軍は非常に厳しい戦いを強いられる泥沼の戦いとなりました。
泥沼の戦いは4年間も続き、独立戦争末期には目立った戦果を挙げられなくなったオランダ軍が一般の集落を襲い、民間人を虐殺して回るというようなことも起きました。
当然、そのような事をしているとオランダは国際的に非難される事となり、加えて、この頃にはアメリカとソ連の二大超大国が睨み合う冷戦の時代に突入していたこともあり、西側陣営への敵対心(オランダはアメリカ側の西側陣営国)が高まることによってインドネシアがソ連寄りの共産主義国になることを恐れたアメリカに独立承認をするように迫られました。
その結果、1949年12月、ハーグ円卓会議(オランダ・インドネシア円卓会議)によって、インドネシアはオランダから独立承認を得ることができました。
このような経緯からインドネシアの人々は非常に親日的であり、独立戦争の時に戦死した1000人以上の日本人はカリバタ英雄墓地他、国立追悼施設に埋葬されており、今現在も多くの花が絶えることなく供えられています。

パイロット適性診断テスト特集
【告知】崇城大学を分析・紹介 入学説明会・オープンキャンパスについて
【告知】 PILOT専門進学塾で行われるイベント紹介
6/30(日) 11時〜 パイロット私大進路相談会
パイロット私大進路相談会は、私大操縦進学希望者向けにパイロット入試の専門家が丁寧にご相談に応じます。
私大操縦の基本情報の説明だけでなく、最新のAI学習教材を使った、学科の体験指導と個別相談ができます。
当日は、現役パイロットが参加し、座談会形式で交流することができます。(20歳以上の参加者様のみ、同日19時頃から開催予定のパイロットを囲んでの懇親会にご参加いただけます)
自社養成、または私大操縦進学を検討されているご本人のみの参加若しくは、保護者様1名様までご同席可能ですが、保護者様だけのご参加はできません。必ずご本人様がお越しください。
6/30私大パイロット進路相談会(中学生〜)開催のお知らせ
6/30(日) 14時〜 自社養成&私大操縦パイロット進路相談会
自社養成&私大操縦パイロット進路相談会は、自社養成志望者と私大操縦進学希望者向けにパイロット入試の専門家が丁寧にご相談に応じます。
自社養成・私大操縦の基本情報の説明だけでなく、自社養成のための進路相談やインターシップ相談、SPI対策相談など、自社養成に特化した個別相談と、私大操縦のための進路相談、面接対策相談、学科相談など、私大操縦進学に特化した個別相談を実施致します。
自社養成についての事前情報を持っているのとそうでないのでは、合格率に大きな違いがあります。現在、自社養成受験を考えている方は、是非ご参加下さい。私大操縦志望者の方も同じく、事前に確かな情報をゲットして、対策するようにしましょう。
当日は、現役パイロットが参加し、座談会形式で交流することができます。(20歳以上の参加者様のみ、同日19時頃から開催予定のパイロットを囲んでの懇親会にご参加いただけます)
自社養成、または私大操縦進学を検討されているご本人のみの参加若しくは、保護者様1名様までご同席可能ですが、保護者様だけのご参加はできません。必ずご本人様がお越しください。
現役パイロットとの懇親会も! 6/30自社養成&私大操縦パイロット進路相談会(6/30後半の部)開催のお知らせ
PILOT専門進学塾 2024年度新規入塾者募集開始
JAMBOが運営するPILOT専門進学塾・シアトルフライトアカデミーの2024年度新規入塾者の募集が開始されました。
PILOT専門進学塾では私大航空操縦・航空大学校受験対策、自社養成対策と有資格者転職対策といった多くのコースをご用意しております。
[告知] PILOT専門進学塾 2024年度 新規入塾 募集開始します
PILOT専門進学塾に入塾するためにはパイロット適性診断テストを受験していただく必要があります。
パイロット適性診断テスト特集
パイロット適性診断テストのご予約
パイロット適性診断テストのご予約は、パイロット相談室の「相談予約」にて承っております。
パイロット適性診断テスト特集