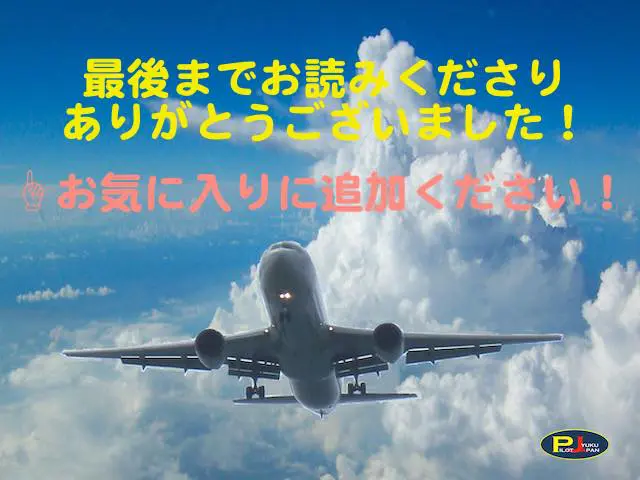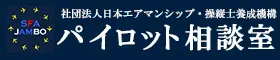ステイ先で学ぶ政歴シリーズ 国内編12〜東京都 三鷹 大学内に残る戦跡〜第1章
皆さん、こんにちは!
JAMBO STAFFの伊藤です。
本日は、東京都三鷹市に来ています!
三鷹といえば、都心から電車で20分足らずで行くことができる、豊かな自然と美しい街並みがウリの都市です。
三鷹は、その落ち着いた土地柄から多くの学校があり、日本有数の学園都市としても有名です。
今や多くの学生が学び、若い活気が漂う町ですが、第二次世界大戦中は現在のような雰囲気ではなく、軍の重要拠点でした。
しかも、今は多くの学生の学び舎となっている有名大学は、その中心となった研究機関の施設を利用して開校されました。
一体、戦時中日本は三鷹の地で一体何を研究していたのか。
今回はその謎について迫っていきたいと思います。

あの有名大学の校舎は昔、秘密研究所だった!?
三鷹には多くの大学がありますが、今回の舞台はICUこと、国際基督教大学です。
国際基督教大学は、言わずと知れた有名大学です。その名の通りキリスト教思想の元建てられたミッションスクールで、平和主義に基づいたバイリンガル教育を行い、リベラルな世界的に高度な人材を育むことを目的として1953年に創立された大学です。
近年では、皇族、秋篠宮家のご息女姉妹が進学されて大きな話題となりました。
そんな戦争とはまるで無関係のように思える国際基督教大学ですが、大学本館とキャンパスの敷地全ては戦時中、「中島飛行機三鷹研究所」と呼ばれた、戦闘機・爆撃機開発の研究所でした。
国際基督教大学は、中島飛行機三鷹研究所の施設を一部改修し、流用した建物なのです。
中島飛行機
読者の中には、「中島飛行機」について知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単に中島飛行機についての説明をしようと思います。
「ゼロ戦」でお馴染みの、三菱重工業は日本人の間でよく知られていますが、確かに三菱重工業が最大メーカーでしたが、戦前、日本には三菱の他にも無数の航空機メーカーがあり、中でも中島飛行機は三菱重工業と肩を並べるほど大きな会社でした。
中島飛行機は1917年(大正6年)に海軍士官出身の実業家(後に政治家)の中島知久平によって創業されました。
創業の経緯としては、ライト兄弟が開発した飛行機の最初の大きな活躍は旅客ではなく、皮肉にも第一次世界大戦での戦闘でした。
第一次世界大戦期には、航空戦力の充実差が勝敗を分ける状況となっていたので、各国とも主に「軍」が主導で航空機の開発を行っていました。
日本も例外ではなく、軍部の研究所が主導で様々な航空機の開発を行っていました。
しかし、飛行機先進国の欧米産の航空機に比べて日本で開発される航空機はどれも見劣りするもので、当時海軍士官だった中島は、国産高性能機開発にあたっては国営(軍部開発)ではなく、民間の航空機メーカーが必要と考え、海軍軍人としてのキャリアを捨て中島飛行機を設立しました。
中島飛行機は、民間でしかできない、自国の航空技術の低さを認めた上で海外先進技術の吸収と模倣、自由な発想による冒険的な改良を重ね、主に陸軍の航空戦力拡大派の将校を巻き込んでいくことによって、設立から約10年経った1930年には日本最大の航空機・航空エンジンメーカーとなっていました。
第二次世界大戦時には、持ち前の技術力を生かし、「一式戦闘機 隼」(実はゼロ戦よりも性能が高かった)や「四式戦闘機 疾風」(終戦時の米軍機をも上回る性能)を開発、生産し、国産ジェット戦闘機も開発していました。
終戦後、GHQの支持により中島飛行機は解体され、二度と陽の目を見ないように徹底的に潰されましたが、中島飛行機はいくつもの会社に分かれて独立しました。
特に、自動車メーカーの「SUBARU(旧・富士重工業)」と、惑星探査機はやぶさで有名な「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」が有名で、現代においても日本のみならず世界に最先端の技術力を用いて影響を与え続けています。
さて、そんな中島飛行機が三鷹の地で一体何を研究、開発をしていたのか。
第2章に続く・・・

【告知】崇城大学を分析・紹介 入学説明会・オープンキャンパスについて
【告知】 PILOT専門進学塾で行われるイベント紹介
6/30(日) 11時〜 パイロット私大進路相談会
パイロット私大進路相談会は、私大操縦進学希望者向けにパイロット入試の専門家が丁寧にご相談に応じます。
私大操縦の基本情報の説明だけでなく、最新のAI学習教材を使った、学科の体験指導と個別相談ができます。
当日は、現役パイロットが参加し、座談会形式で交流することができます。(20歳以上の参加者様のみ、同日19時頃から開催予定のパイロットを囲んでの懇親会にご参加いただけます)
自社養成、または私大操縦進学を検討されているご本人のみの参加若しくは、保護者様1名様までご同席可能ですが、保護者様だけのご参加はできません。必ずご本人様がお越しください。
6/30私大パイロット進路相談会(中学生〜)開催のお知らせ
6/30(日) 14時〜 自社養成&私大操縦パイロット進路相談会
自社養成&私大操縦パイロット進路相談会は、自社養成志望者と私大操縦進学希望者向けにパイロット入試の専門家が丁寧にご相談に応じます。
自社養成・私大操縦の基本情報の説明だけでなく、自社養成のための進路相談やインターシップ相談、SPI対策相談など、自社養成に特化した個別相談と、私大操縦のための進路相談、面接対策相談、学科相談など、私大操縦進学に特化した個別相談を実施致します。
自社養成についての事前情報を持っているのとそうでないのでは、合格率に大きな違いがあります。現在、自社養成受験を考えている方は、是非ご参加下さい。私大操縦志望者の方も同じく、事前に確かな情報をゲットして、対策するようにしましょう。
当日は、現役パイロットが参加し、座談会形式で交流することができます。(20歳以上の参加者様のみ、同日19時頃から開催予定のパイロットを囲んでの懇親会にご参加いただけます)
自社養成、または私大操縦進学を検討されているご本人のみの参加若しくは、保護者様1名様までご同席可能ですが、保護者様だけのご参加はできません。必ずご本人様がお越しください。
現役パイロットとの懇親会も! 6/30自社養成&私大操縦パイロット進路相談会(6/30後半の部)開催のお知らせ
PILOT専門進学塾 2024年度新規入塾者募集開始
JAMBOが運営するPILOT専門進学塾・シアトルフライトアカデミーの2024年度新規入塾者の募集が開始されました。
PILOT専門進学塾では私大航空操縦・航空大学校受験対策、自社養成対策と有資格者転職対策といった多くのコースをご用意しております。
[告知] PILOT専門進学塾 2024年度 新規入塾 募集開始します
PILOT専門進学塾に入塾するためにはパイロット適性診断テストを受験していただく必要があります。
パイロット適性診断テスト特集
パイロット適性診断テストのご予約
パイロット適性診断テストのご予約は、パイロット相談室の「相談予約」にて承っております。
パイロット適性診断テスト特集